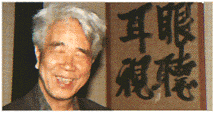
人間の二足歩行が、その進化の過程で前足を歩行から解放し、脳の発達を促すといった
重要な役割をはたしてきたことはよく知られているところです。
子どももそのような「足」について深い関心を持ち、数多くの作品を書いております。
あしのうら
小学二年 えんどう ゆうすけ
あしのうらにすみをつけたら
ぴりっとしみた
がようしの上にのっかったら
くろいあしあとがついた
大きいゆびと小さいゆび
土ふまずが ひっこんでいる
このあしで
ぼくは たっている
あるいていく
はしる
とぶ
この まっくろいあしのうらを
土につけて
ここには画用紙の上に黒々と印された自分の足形から響いてくるものをそのまま受けとめ、
そのまま書き綴った力強さが脈打っています。
そして、飾り気のない表現の中で、足の本質をきちんと言い尽くしています。
足
中学一年 渡辺 としお
太陽がガンガン照っている
あせがシャツの中を流れるのが
ハッキリわかる
きょうは田植だ
かあちゃんとじっちは
さっきからわき目もせず
苗をにぎって腰をまげたままだ
すごく速い
苗が少しになっていくと
うしろには
苗のうわったあとが帯のようだ
足がかゆい
ふと見るとヒルに食われたのか
どろまみれになった足のまわりを
赤ぐろい血がドロドロ流れている
ぼくはびくっとした
ぼくの本当の足でない
田んぼの中に
どろまみれのぎそくの様な足が
きみ悪く見えた
これは強い印象に残っている三十年前の詩です。そのころ農家の子どもたちは
大切な労働力だったのです。
歩く
養護学校中学部 吉川 あゆみ
歩くってすばらしい
歩いて感じる美しさ
自分で歩けるというのは幸福をはこぶもの
一歩 二歩 形が悪くとも
自分で歩くすばらしさ
でも 今日の私ころんでばっかり
足がからむ
そんな時だんだん悪くなるように感じる
そして友達だけが良くなっていくように
思ってしまう
私は みんなを後ろから見送るようには
なりたくない
きっとお母さんおこるだろう
まっすぐにかっこう良く歩く姿を
お母さんに見せるのが私の願い
その日まで私はがんばろう
失ってみてはじめてその意味を知ることができる、とよく言われますが、
私も失明によってこの言葉を体験いたしました。
作者もまた、リハビリテーションの真っ最中ですが、それをささえてくれるのが
やはり母なのです。
ぼくの足
小学六年 斎藤 定吉
体育館をはしっていると
パタパタと どの足もひびく
中 略
ぼくの足からドーンドーンとひびく
その足は自転車のペダルをふんだ足
ろうかをはしっておこられた足
畑をこえてどなられた足
そんなことを考えながら走りまわった
川で水およぎしてくいにぶつかった足
けんかの時けっぽった足
木に登った足
お祭にだれかにふまれてないた足
中学校にいったら
この足で土台をつくるんだ
ぼくはとびあがりながら
走りまわった
このように見てきますと、足は人類の歴史であると同時に人生でもあるのです。
そして、ここまできて、ハッと気づかされるものがありました。
それは良寛の詩の一節です。
―夜雨草庵のうち、双脚等閒にのばす―
つまり、夜の雨を聞きながら草庵のうちで、何の気づかいもなくゆったりと
足をのばす、というほどの意味になりましょう。
その脚が人生であり、人類であり、そして涅槃を意味するのではないか、と。
(平成五年 青い窓四月号に掲載)
**********************************************************
